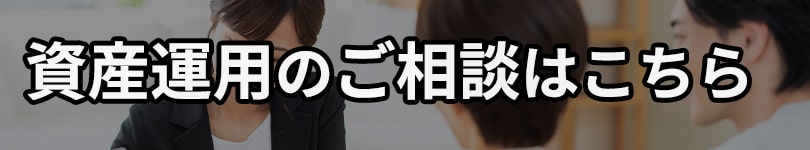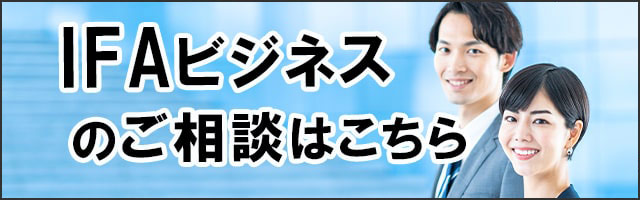運用の税制を優遇する制度であるNISA (少額投資非課税制度)。
そんなNISAが、2024年からは新NISAとして大幅に改正される予定となりました。
マネカレでは、新NISAのポイントとなる要点や制度・注意点などをやさしく解説していきます。
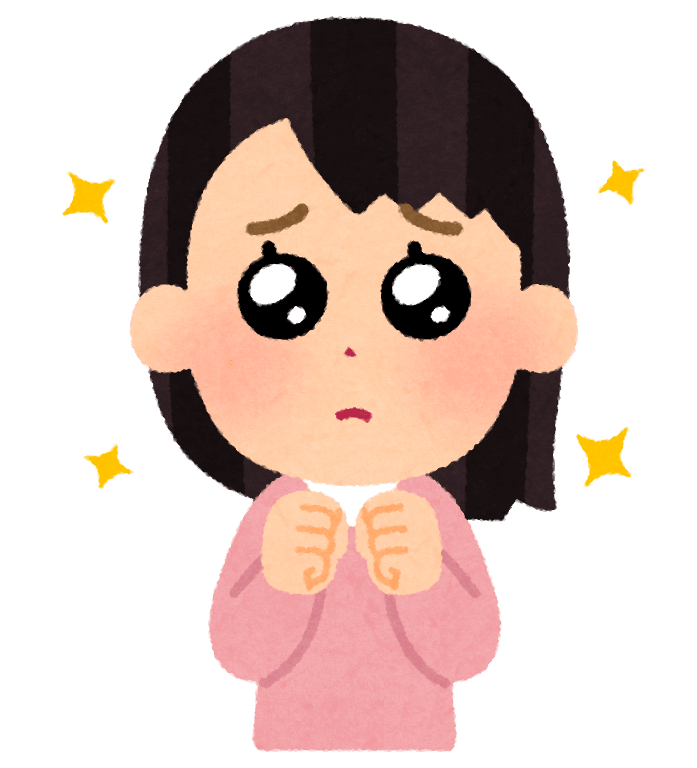
新NISAがどんな制度なのかを知りたい!

やさしい内容で新NISAの解説をしてほしい!
といった方は、ぜひご覧ください。
新NISAの情報について
新NISAに関連する情報については、各種法制度などによって変更されます。
今後の審議状況などに基づいて、情報発信・更新を随時行う予定です。
最新情報などをはじめとしたご質問については、マネカレのお問い合わせフォームまたはPWM日本証券 (運営会社)にご相談ください。
新NISAのポイントとなる3つの要点
2024年にスタート予定の新NISA制度は、
- 投資金額の非課税枠が増える
- 非課税の期間が無期限になる (恒久化)
- 売却すると投資枠が復活する
の3つのポイントに大きく分けられます。
まずは要点となるポイントから見ていきましょう。
1. 投資金額の非課税枠が増える
現行のNISA
これまでのNISAで購入できる金額 (非課税投資枠)は、
- 一般NISA: 年間120万円
- つみたて: 年間40万円
のどちらかを選択する方式でした。
新NISA
1年間あたりの非課税枠
新NISAで1年間あたりに購入できる金額は、最大360万円に拡大しました。
- つみたて投資枠: 年間120万円
- 成長投資枠: 年間240万円
を併用するかたちで利用することができます。
生涯あたりの非課税枠の上限
新NISAでは、生涯における非課税枠の上限が1800万円に設定されました。
それぞれの投資枠については新NISAの制度をやさしく解説をご覧ください。
2. 非課税の期限がなくなる
現行のNISA
これまでのNISAでは、非課税で運用できる期間(非課税保有期間)として、
- 一般NISA: 5年
- つみたてNISA: 20年
といった期限がありました。
新NISA
新NISAでは、非課税で運用できる期間が無期限となりました。
NISAの恒久化と呼ばれることもあります。
3. 売却すると投資枠が復活する
現行のNISA
これまでのNISAでは、保有していた投資商品を売却しても、投資枠が戻ることはありませんでした。
新NISA
新NISAでは投資商品を売却すると、翌年にそのぶんだけの金額が復活します。

投資枠を上限まで使い切ったので、もうNISAで投資できない~。
などのような悩みから解放されるわけです。
新NISAの制度をやさしく解説
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 1年あたりの非課税枠 | 120万円 | 240万円 |
| 生涯投資上限枠 | 1800万円 | |
| 1200万円 | ||
| 非課税となる期限 | 無期限 (恒久) | |
| 投資できる商品 | 指定された投資信託 |
|
| 制度の併用 | 併用できる | |
1.「つみたて投資枠」と「成長投資枠」
現行のNISAでは、一般NISAとつみたてNISAに分かれていました。
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠といった新しい制度に変更される予定です。
つみたて投資枠
投資信託のなかから、指定された銘柄を選んで運用するのがつみたて投資枠。
1年間あたりに投資できる金額は最大120万円です。
どんな投資信託を選べるの?
金融庁によって、

これなら投資初心者でもはじめられる!
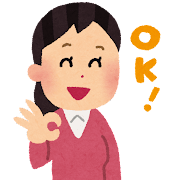
長期的な資産運用にも向いてる!
などといった基準をクリアした投資信託の銘柄だけを選ぶことができます。
実際に選ぶことができる投資信託の銘柄は、現行のつみたてNISAとおなじとなる予定です。
どんな人に向いてるの?
- 投資初心者
- 長期的な積立をしたい人
- 分散しながら投資をしたい人
成長投資枠
投資信託や上場している株式などに投資できるのが成長投資枠。
1年間あたりに投資できる金額は最大240万円です。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用できる
これまでのNISAでは、一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選ぶ必要がありました。
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠は、いっしょに併用して運用することができます。
どちらの投資枠も手数料・購入方法・選択できる銘柄などの特色があるので、

運用する余裕資金がある!
という方は使い分けながら活用していくのもいいかもしれません。
新NISAの2つの注意点
現行のNISAから新NISAの「ロールオーバーができない」
非課税となる期間が無期限(恒久)になった新NISA。
そのために現行のNISAでは行われていた、非課税の期限を延長するための制度であるロールオーバーが廃止されることになりました。

現行のNISAと新NISAはまったくの別物!
の扱いとなるので、新NISAへのロールオーバーはできません。
これまでNISA口座で運用していた方は、注意してください。
2. 成果をだすことでNISAの効果がでる
NISA口座での運用で損失をだしてしまった場合は、損失した分の金額を控除する損益通算ができません。
つまり、

利益をだすことで、はじめてNISAの効果がでる!
ということ。
これは現行のNISAも新NISAも考え方はおなじです。
新NISAのご相談はPWM日本証券へ
資産運用で継続して利益をだすためには、
- 自分で資産運用の勉強をしながら、経験を積む
- 資産運用のプロにアドバイスをもらいながら運用する
のどちらかを選ぶ必要があります。
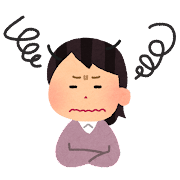
自分で勉強するのも大変だし、できるだけ失敗したくない……。
という方は、資産運用のプロにアドバイスをもらいながら運用するのがいいかもしれません。
マネカレの運営会社であるPWM日本証券では、在籍するアドバイザーが新NISAや資産運用にまつわるご相談にお応えいたします。

新NISAについて、もっと詳しく教えてほしい!
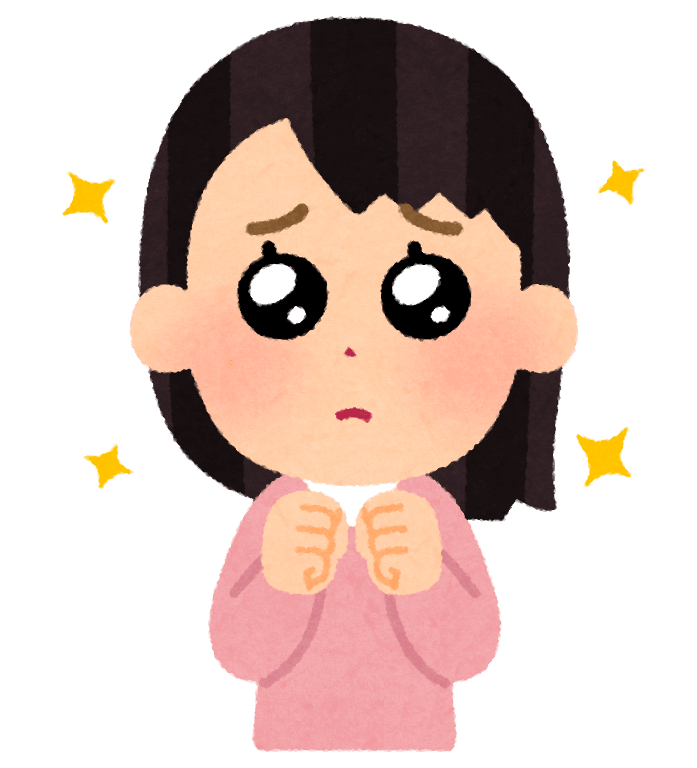
基本からNISAを教えてほしい!
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お電話でもご相談専用フォームでも受付中です。